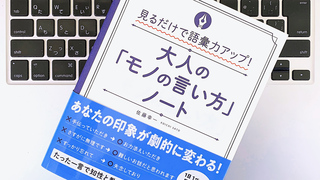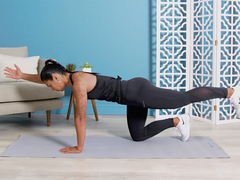NPR:英語では「ギーク」や「ナード」と呼ばれる「オタク」。この言葉を聞いたとき、どのような人物を思い浮かべるでしょうか? メガネをかけた、チェックのネルシャツを着た男性を思い浮かべたとしたら...完全にオタクに対する固定観念に縛られているといえるでしょう。
米メディア「NPR」では、オタクに対する固定観念について、またそれがどのように人の意思決定を左右するかについて、興味深い研究結果を交えて掲載しています。
「 "科学者=オタク" ではない!」という主張
NPRで同僚のライターであり科学者でもあるMarcelo Gleiser氏は最近、このような内容の記事を書きました。
オタクな科学者はいる。でも、クールな科学者だっている。バイクを乗り回すような科学者も(たとえば、僕のように)。サーフィンが好きで、エレキギターを弾く科学者もいる。医者や弁護士と同様に、科学者も多様性に富んでいる。無神論者もいれば、神を信じている者もいるし、バスケが好きな人もいれば、ホッケー好きの人もいる。(中略)
一般化することで、ありのままの実像が見えなくなる危険性がある。また、こうした一般化は特に科学者に対して顕著だ。
この記事に対して寄せられた次のようなコメントが印象に残りました。
科学者に「クール」なイメージを持たせようとする考えには100パーセント賛成できない。大事なのは、科学者をクールに見せることではなく、オタクをクールに見せることだ。
米国で始まった「ナードプライド」運動
オタクをクールに見せようとする考え方が始まったのは、1990年代にさかのぼります。90年代、マサチューセッツ工科大学(MIT)で「ナードプライド」運動が始まったのです。1993年のNew York Times誌の記事にはこのように書かれています。
よく第三者が「オタク」という言葉を侮蔑的なニュアンスで使うことがあるのに対して、MITではその言葉は「ファッション以外のすべてのことに興味がある者」という定義で浸透しています。
2006年の初期には、5月25日が「ギークプライドデイ」として宣言されました。『スター・ウォーズ』の1作目が公開された日付にちなんで。
オタクはもはやマイノリティではなくなったと感じられることもあります。漫画が原作の映画がヒットしたり、オタクである主人公が登場する『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』がテレビシリーズになったり、シリコンバレーでのサクセスストーリーが尊敬の念と共に語られたり。2010年にはコンピュータエンジニアのバービー人形も登場しました(MITの定義に反して、バービー人形はファッションにもかなり興味を持っているようでしたが!)。
払拭が難しい「オタク=男性」というイメージ
コンピュータエンジニアのバービー人形はさておき、多くの人のオタクに対する見方というのは非常に偏ったものです。特に顕著なのは、男性的なイメージと結びついているという点です。コスモポリタン誌上の「ギークなものをクールにする女子」4名のひとりであるRae Johnsonは、先月次のように書いています。
オタクはこういう見た目であるべきという思い込みが蔓延している。そのイメージに合っていなかったら、本物のオタクではないと責められるのだ。
Elise Andrew氏は、もっとも人気を集める科学系Facebookページ『I ****ing Love Science』の運営者。彼女が自分は女性であることを明かすと、次のような驚きの声でコメント欄が埋め尽くされました。
「え...女性だったの?」
「オーマイゴッッド! かわいい! 女の子! 女の子が運営していただなんて思いもしなかった。しかも、かわいい子だなんて! 本当にごめんなさい」
「全く想像と違ってた! 30代のハーバード卒のギークが運営してるもんだと、てっきり思ってたよ」
女性のオタクというのが矛盾した存在というわけではありませんが、しかし実際に蔓延しているイメージはこんなものです。「オタクは分厚いメガネをかけている若い白人男性で、OSに関して強いこだわりを持っていて、スターウォーズのフィギュアを集めている」といったもの。そうしたイメージが科学者にも当てはまるのであれば、オタクをクールに見せようとする試みは、そうしたイメージにはまる存在にとっては魅力的なことかもしれませんが、同時にそのイメージに当てはまらない存在を、無意識に除外していることにもなります。
オタクに対するイメージが女性の意思決定を大きく左右する
残念なことに、そうした傾向を示す研究結果が増えてきています。職種ごとに付けられているイメージが、その職種に就くための妨げになっているというものです。
2009年に発表された研究結果は衝撃的な内容でした。心理学者の研究チームは、女子大学生がコンピュータサイエンス(正にオタクな専攻です)に興味を持つ背景として、どのような要因があるかを調べました。研究者は、対象の女子学生を2つの部屋に分け、それぞれアンケートに回答してもらいました。
この2つの部屋ですが、片方はSFテレビドラマの『スタートレック』のポスターや漫画、ビデオゲーム、ジャンクフード、炭酸飲料などを置いた、「オタクな」雰囲気の部屋でした。もう片方は、風景の写真のポスター、アート、ミネラルウォーターのボトル、健康的なスナックなどを置いた、「自然な」雰囲気の部屋でした。
すると、オタクな部屋でアンケートに回答した女子学生は、同室でアンケートに回答した男子学生よりもコンピュータサイエンスに対する興味がずっと低かったのに対して、「自然な」部屋で回答した女子学生はその部屋で回答した男子学生と、ほぼ同レベルの興味をコンピュータサイエンスに対して示すという結果になったのです。
つまり、オタクに対するイメージを助長する雰囲気か、もしくはそうしたイメージを壊すような雰囲気の環境にいるかどうかで、コンピュータサイエンスに対する感じ方が大きく変化する結果となったのです。
多様なイメージを示すことで、固定観念を壊すことができる
ということはつまり、より多様なイメージを築ければ、オタクに対するイメージを「クール」なものへと変化させることができるのでしょうか? 今年のはじめに発表された研究結果は、その可能性を示唆しています。
心理学者の研究チームは大学生に、偽の内容であることを隠して、2つの架空のニュースを読んでもらいました。1つ目のニュースは、コンピュータサイエンスはオタクによって支配されているという内容のものです。
最新の研究によると、コンピュータサイエンスを専攻する学生の3人にひとりが、「自分はオタクである」と回答した。その割合は数年前から変化していない。
(中略)キャンパスを歩いていると、コンピュータサイエンス学部の建物に向かっているであろう学生を見つけるのは簡単だ。
コンピュータサイエンスを専攻する学生のイメージとしてまず思い浮かぶのは、ひょろっした長身のひ弱そうな学生で、ださいシャツを着ていて、前髪がまっすぐ切りそろえられていて、メガネをかけているというイメージだ。
連想ゲームにおいて、「コンピュータサイエンティスト=オタク」という連想は永遠に変わることはないだろう。
別のグループの学生に読んでもらった2つ目のニュースの内容は、上記とは全く逆のもので、コンピュータサイエンスはもはやオタクによって支配されていないというものです。
最新の研究によると、コンピュータサイエンスを専攻する学生の中で、「自分はオタクである」と回答した割合が、数年前と比較して大幅に減少したことが判明した。
(中略)キャンパスを歩いていると、実に多様な学生がコンピュータサイエンス学部の建物に向かっているのを見ることができる。
コンピュータサイエンスを専攻する学生のイメージとしてまず思い浮かぶのは、もはやひょろっした長身のひ弱そうな学生で、ださいシャツを着ていて、前髪がまっすぐ切りそろえられていて、メガネをかけているというイメージではない。
連想ゲームにおいて、「コンピュータサイエンティスト=ギーク」という連想はもはや古いのだ。
どちらのニュースを読んだかによって、コンピュータサイエンスに対する学生の興味が大きく左右されることが判明しました。ただし、それは女子学生に限られたことです。2番目の、これまでのオタクに対するイメージを払拭するようなニュースを読んだ女子学生は、最初のニュースを読んだ学生よりも、コンピュータサイエンスに対する興味が高いという結果になったのです。なお、男子学生については、そうした違いは見られませんでした。
この研究を行ったVictoria Plaut教授に、この研究について次のようなコメントをもらいました。
架空ニュースの中身は男性についての内容であったにも関わらず、女性のコンピュータサイエンスに対するイメージに大きな影響力を与えることに、驚きました。ニュースの設定が男女比のバランスがとれたものだったとしても、おそらく結果は同じでしょう。裏を返していえば、女性の数が少ない環境においても、固定観念を打ち消すことで、女性の参加を促進することができるのです。現実の男女比が全く影響しないとは言えませんが、楽観的な見方をすれば、女性の雇用を促進するためにできることは多くあるということです。
Plaut教授は、コンピュータサイエンスのような専攻において、女性の比率が少ないのは、能力の低さが原因ではないと強調します。
他の研究においても興味深い結果が示されています。それは、女性は学科の成績が悪いために専攻から外れるのではないということです。主専攻の前過程における科目においては、女性の成績は男性と同レベル、もしくはそれ以上なのです。
女性の能力が高いという事実は、科学・テクノロジー・工学・数学といった分野で女性の参加を阻んでる社会的な要因を理解して、変化をもたらすべきであることを示しています。そうした分野へ男女ともに公平に参加できるようにし、才能を最大限に活かすために。Plaut教授の言葉を借りれば、ポイントとなることはシンプルです。「その分野のイメージを多様なものにする」というものです。
「多様性」こそが重要である
残念ながら、それを実現するのはたやすいことではありません。しかし、その試みは「オタクをクールなものにする」という試みと対立するものではありません。Plaut教授は次のように話しています。
その分野に多様性をもたらすことは、オタクであることに誇りを持つという考えは対立しません。ある分野が1つのグループのみで構成されているというイメージを作らないことです。たとえば、あるテレビドラマに登場するキャラクター全員が科学者であり、彼らがオタクとして表現されれば、そのドラマはそうした固定観念を広めることとなり、女性の関心を引きつけることはできないでしょう。
そんなわけで、冒頭で紹介したMarceloの「クールな科学者」という提案は、確かに今私たちがまさに必要としているものかもしれません。「クール」という概念が受け入れられていることを考えると。
バイクに乗り、エレキギターを弾き、サーフィンを楽しむ科学者だけでなく、ファッションが好きなエンジニア、お菓子作りが好きな物理学者、サルサを踊る科学者など、いくらでも例を挙げることができます。
ちなみに、科学と科学者に対する固定観念に関する研究について、Marceloに話したところ、彼はさらに次のような意見を述べてました。
興味深いのは、科学者の多くが実際にはクールな人たちだということだよ。みんな、実際の彼らにもっと注目すべきだ。テレビドラマや映画で描かれる科学者ではなく。だって、実際の科学者こそが本物なのだから!
そうした多様な科学者像にくわえて必要なのは、科学自体がいかにクールかってことだね。一生をかけて、自然や人間についての謎を解明しようと試みることは、まさにトム・ストッパードが戯曲『Arcadia』で伝えた「我々に関わることを理解したいと思うこと」 なのだから。
そしてまた、多様性を保つということは「従来の」オタクにとっても居心地のよい環境を保つということでもあります。誇りを持ってアニメ柄のソックスを履けるような環境を。
Scientist = Geek Is A Dangerous Equation | NPR
Tania Lombrozo(訳:佐藤ゆき)
ランキング
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5